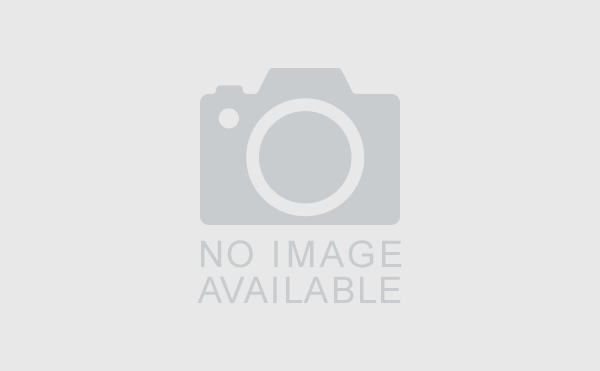断捨離とクレームの関係について熟考【断捨離停滞を防ぐために】
くれこはクレーマーです。自己紹介はこちらです。
くれみすと。アラフィフのワーママ。現在は旦那さんと会社経営をしている。
20年来のクレーマー。大小あわせて延べ300件のクレームを企業に実施。
クレーム経験が人生に活かせることを知ってしまった人。
クレーム先業界は地方自治体、銀行、医療、教育、保険、旅館、飲食店、物販、メーカー、サービス業…と多数。
クレーム入門と検定を作るのが目標。
断捨離している方、多いですね。くれこもその一人です。
約一年に渡るモノ減らしで、自分の持ち物は10分の1になりました。
およそ1200のアイテム(個人分のみ、家族分含まず)を所有していましたが、
現在は120くらいまで減らしました。
これだけモノが減ったおかげで、探しものの時間が激減しました。
これはほんとうにありがたい話で、これだけでも断舎離した甲斐がありました。
紛失、忘れ物の類いは「ほぼゼロ」を達成しました。
モノ減らしの途中として、無くし物が無くなってよかった、という話です。
断捨離はライフワークになりました。
いわゆるモノがあふれる時代ですので、現代病ですね。
カッコよく言うと「現代病との戦い」かもしれません。
コツコツとあきらめずに、自分のペースで断捨離を頑張っていきたいものです。
さて本題ですが、今回はクレーマーが考える断捨離について。
クレームと断捨離ってどんな関係かを、クレーマーが熟考しました。
なぜ熟考したかというと、断捨離が行き詰まった時期がきたからです。
断捨離が、止まった!
断捨離が進まなくなってきたり、何を捨ててよいかわからなくなったり、
断捨離がんばってるけど、リバウンドしだした、とかありますよね。
先程のとおり、くれこは1200アイテムを120アイテムまで減らしていますが、
減らす過程で何回かの停滞期を迎えました。
「もう、捨てるもの、無いわ。」
と開き直りたくなる時期が何回もありました。
断捨離が停滞する理由は「向き合えてないこと」、だと気づいた
断捨離をしていると避けて通れない「向き合い」と遭遇します。
モノと向き合うというよりは、モノを通じて3つの事に向き合う必要があるんじゃないでしょうか。
自分との向き合い
過去との向き合い
他者との向き合い
3つの向き合いですが、結局は自分との向き合いなんでしょうか。
あとの2つはそのおまけくらいの事で、これらとの向き合いの結果がモノ減らしにつながるんだと思っています。
前置きが長くなりましたが、断捨離にもクレーム行動が役に立ちます。
「断捨離とクレーム」はなぜ関係するか、掘り下げていきたいと思います。
そのモノと自分の関係性を見つめる【クレーム思考】
クレームを一度でもしたことある人ならわかると思いますが、
クレームときは、そのモノやサービスについて考えます。
ある企業に「私の買ったあなたの商品に問題があるかもしれません。」
と相談する以上、こちらにも責任があります。
当然、ネットに同じような情報が出ていないかとか、検索しますよね。
ネット情報で解決する程度なら、わざわざクレームする必要なんてありませんので。
間違いが少ないように、自分なりに、考えることになります。
何が問題か、一般的にはどうか?、色々考えたり調べたりします。
それからクレームするので、ここまででかなりの思考をすることになります。
そうすると、「あれ、これはなんで買ったんだっけ?」
なんていう根本的な問題にたどり着きます。
たとえば買った理由はこんな感じでしょうか。
「やすかったから」
「急いでいたから」
「ちょうどこまっていたから」
「問題解決できそうだったから」
「CMやサイトが好感持てたから」
「よい口コミがあったから」
理由はさまざまですが、失敗にも向き合わなければいけません。
「ちっきしょう、完全にCMに騙された」
「口コミがやらせだったのか」、などなど苦々しい気持ちになることもしばしばです。
でも、これを「ま、いいか」と放置すると、クレームはできません。
放置すると、道具と言うモノは残ってしまします。
モノには感情をぶつけようがないので、放置です。
過去に向き合わないから放置、捨てたくないからモノは増える一方です。
モノ減らしからは一歩遠ざかることになります。
クレームしないで捨てるが断捨離には一番良い、が
クレームなんてめんどくさいから、捨てよう!と思えれば問題ありません。
要らなければ捨てればいいんです、それができれば断捨離で悩むことはありません。
ガンガン捨ててスッキリすれば目的達成ですが、そうもいかないから断捨離は停滞するんだと思います。
炊飯器で例えてみたい
とつぜんですが、私はインスタントポット(電気圧力鍋)という調理家電が大好きです。
このブログにもいろいろ書いています。
インスタントポット関連の記事はこちらです。
インスタントポットが好きすぎて深掘りしている変な人です。
私はクレーマーですが、インスタントポットには一度もクレームしたことはありません。
10,000円台で米も炊け、焼く、蒸す、煮る、と一台で幅広い活用法があり、
断捨離にはもってこい調理家電です。
インスタントポットは地味なトラブルは多いですが、
いつもかんたんに回避できるからクレームしたことありません。
もっともっと良さを広めたいくらい、インスタントポットに感謝しています。
さて、本題に。
仮に、高額な60,000円くらいの炊飯器を買ったとします。
高いだけあり、美味しそうなご飯が炊けそうですね。
その宣伝文句が「古米でも美味しく炊けます」と書いてあった、とします。
さっそく購入して使ってみましたが、古米を炊いても「美味しくない」と思いました。
ここで分岐が発生します。
分岐A「古米だから、しかたないよね、期待しすぎちゃった」と思ってあきらめる
分岐B「いや、メーカーが美味しく炊けると言ってるんだから、なにか方法があるはず」
と思い、ネットで情報収集する
分岐Aの人はあきらめがはやすぎますね。
分岐Bの人は「美味しく炊ける」という情報記事を見つけ、
その真似をしますが、うまく行かないとします。また分岐が発生します。
分岐C「うちのお米の種類がわるいのかな?」と諦める
分岐D「いや、他の人ができてるということは、何か問題があるはずだ。」問い合わせを検討する。
ここまでくれば、メーカーにクレーム(相談)してもいいかもしれません。
固有の問題か、商品自体のレベルか、判断しなくてはなりません。
ここまで向き合って、はじめて「クレーム」行為にたどりつきます。
頑張ってクレームした結果はこんな感じでしょうか。
- 操作方法を間違っていただけで解決した
- 初期不良による交換となった
- あまりにも誇大広告ということが分かり、返品や返金を要請した
相手もあることなので、相談して決めることになります。
向き合ってケリをつけるために、相談することになるんです。
クレーム先は「向き合うべきモノの代弁者」となります。
クレームするとモノと対話できるようになる【モノの擬人化】
通常、モノと向き合うと、モノはなにも答えてくれません。
でも、クレームすると、売った人が代弁してくれるんです。
これがモノの擬人化です。
そのおかげとは、このモノをどうするか、使うのか、返すのか、捨てるのか、判断しやすくなるんです。
これはかなりモノと向き合いやすくなります。
アメリカのあるミニマリストは、モノが捨てられないとき、
「一人二役でモノと話し合ってみたらいい」とも言っています。
自分対モノの対話です。なるほど、ミニマリズムは深いな、と思いました。
そのミニマリストさんの書籍はこちらです。
この本は本当に深い本で、断捨離うまくいかないときは必読です。
書籍買うと、またモノが増えますので、電子書籍のほうがいいですね。
さらにもういっちょ、断捨離、ミニマリズムの本は書籍よりオーディオブックを断然おすすめします。
オーディオブックは勝手に読んで聞かせてくれるので便利です。
この本を耳で聞きながら、断捨離するのがベストです。
はかどりますよ、断捨離。
AmazonのAudibleは聴き放題になりましたので、一度おためししてみたほうが良いかもしれません。
どうしても捨てられないモノに向き合うために、クレームしてみる
そんなわけで、クレーム行為はモノとかなり向き合う必要があるんです。
モノ自体には意思も思考もないので、それを売った人を通じて向かい合うことができます。
そして自然にそのモノに最終判断を下せる可能性が出てくるんです。
捨てるのがベストなのはわかっているが
断捨離したいんですから、捨てるのがベストなのはわかっているんです。
だけどその手前のプロセスで、くじけるんです。
断捨離にはいつも「必要か、必要じゃないか」が問われます。
いつでも自己解決出来る人には、断捨離なんて必要ないかもしれません。
自己解決できないから、家はモノだらけなんですね。
自己解決できない人だから、モノ減らしができないんです。
私がまさにそういう人でしたので。
なので自己解決できない人は、使っていないのに捨てられないモノの販売者に相談をしてみるといいです。
なぜ使えないか、なんで不便なのか。
なにか理由があるから使ってないんです。
ほんとうはいいモノかもしれません、あなたが知らないだけかもしれません。
良い使い方を教えてもらう機会になるかもしれませんし、
もういいやと諦め、モノを捨てられるきっかけになるかもしれません。
そんなクレームきっかけでモノと向き合う機会ができるので、
モノに向き合った経験値が積み重なります。
そしてクレームをしてみた経験は断捨離の次のステップに役に立つことになります。
クレーム(相談)は事前にもできる【断捨離の「断」】
クレームになれると、買う前に相談することもできるようになるんです。
これは断捨離でいうところの「断」と思いますが、余計なモノを入れづらくなっていきます。
クレーム(相談)で進む判断→断捨離の「捨」
捨てるためには判断しなくてはいけません。
判断するための行動がクレームなので、判断にすすむ第一歩、になります。
クレーム(相談)で出る結果→断捨離の「離」
実はこれが最も重要と言っても過言ではありません。
理由は簡単です。
クレーマー的には「問題解決してくれなかったメーカーや企業のモノは利用しない」ということになります。
相談したのに解決してくれないモノを売る企業、もう信じなくていいですよね。
そこの商品やサービスはもういらないですよね。
ちなみにくれこがクレームの結果「もう二度と利用しない」と決めたメーカーはこちらです。
クレームしたおかげで、未来永劫、選択肢が減るんです。
これはすごい効果で、未来の自分への大きな贈り物になるんです。
自分を大事にするために頑張るのが断捨離なので、未来の自分の選択肢を減らしてあげるのは
モノを減らす以上の価値があるかもしれませんね。
くれこは利用したくない企業についてツイートしています。
はい、ソフトバンクです。
ほんとにもうこりごりです。このグループはかなりのカスタマー泣かせです。
まあソフトバンクが良いか悪いかはさておきまして。
この例で言いますと、私にとってソフトバンクは「離」となりました。
おそらく未来永劫、ソフトバンクのサービスは使うことありません。
私の人生の選択肢に「ソフトバンク」という文字は消えました。
このさきソフトバンクのサービスを検討する必要がないんです。
小さく見えますが、選択肢が明確に消えるというのは、とてもメリットがあります。
断捨離のメリットはムダな思考回数を減らすことにある
モノが思考回数を奪うということを聞いたことありますか?
くれこも最初は「は?」って思いましたが、今となればわかります。
雑然と散らかった部屋にいると、いろいろなモノが目に入りますよね。
捨てなきゃいけないな、と思っている読んでいない本があったとします。
そのモノは目に入るたびに「私のこと、どうします?覚えてます?」
と訴えかけてくるんです。
その度に「ああ、捨てなきゃ」とか「メルカリに出さなきゃ」とか言ってあなたの思考を奪います。
家族にいつも「今何時?」とか聞かれたとき、
「自分で時計見ろや!」と思いませんか?イラッとしませんか?
人は他人からの思考回数を奪われるのには敏感ですが、
モノから思考回数を奪われるのには意外と鈍感なんですね。
そんな感じで限りある自分の思考を奪われているから、
モノ減らしたほうがいいよ、というのも断捨離の大事な要素です。
少し聞いてください。くれこは、断捨離をはじめてから、台所スポンジをやめました。
台所スポンジやめてお皿どう洗うの?と思うかもしれませんが、
それは汎用性が高いスポンジタオルに替えています。
これ1つでお皿洗い、風呂洗い、掃除までできます。
おかげで、お皿洗いのスポンジを検索したり、お風呂洗いのスポンジを検討したり調べたり、
消毒したりするメンテナンスをする必要がなくなりました。
とっても楽になりました。詳しくは下の記事をどうぞ。
考えてみたら台所にスポンジって要らないわね、という話
別にスポンジにクレームしたわけではありませんが、
切り替えたきっかけは「台所スポンジは汚い」という記事でした。
これだけでも思考回数をかなり減らすことができました。
くれこは元来、小心者で日和見主義で八方美人です。
そんな私ですらたまたまクレームできたから、モノやサービスと向き合うことができるようになりました。
クレームは断捨離の役に立ちました、ということです。
まとめます
「まあいいや、で放置」で済むほど断捨離は甘くなかったです。
モノや人と向き合うって、かんたんじゃないですよね。
まして断捨離は自分とも向き合わなければいけません。
モノと向き合わないと家はモノだらけになってしまいますし、
人と向き合わないと言いたいことも言えずに泣き寝入りしてしまったり。
そんなこんなで健やかな状態から遠ざかってしまうんだと思っています。
「向き合う」方法のヒントになる「クレーム」
そんな簡単じゃない、向き合いの入り口として、クレームはわかりやすいです。
クレーム感覚が高まれば、モノとの向き合い方は大きく変わります。
一見関係なさそうなクレームと断捨離ですが、実は意外と関係性がある、
ということで、みなさまの断捨離促進のきっかけになればこれ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。